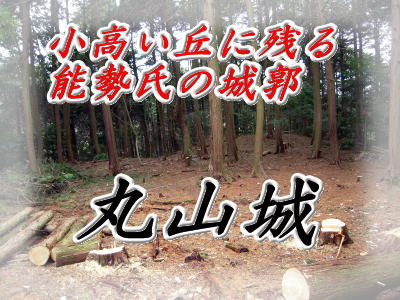丸山城主郭
|
能勢頼国の築城と伝えられる。
能勢氏は近隣の鉱産物を掌握し勢力を拡大したと伝えられている。
1577年織田氏従属に応じなかった為に能勢頼道は織田氏に従属する塩川長満に謀殺された。
この時、塩川氏は丸山城に迫ったが頼道の弟、頼次は大槌峠にて塩川軍を粉砕した。
その後、明智光秀に従属したが本能寺変の後、明智氏が羽柴秀吉に滅ぼされると秀吉軍が能勢領に進軍し頼次は逃避し丸山城も秀吉軍により落城した。
頼次は各地を巡り徳川家康の小姓となり関ヶ原の戦いで戦功を立て旧領を与えられ復帰した。
領民は祝福し頼次を迎えたと伝えられる。
頼次は入城後まもなく丸山城より地黄陣屋に移り、能勢氏は明治維新まで小さな藩として存続した。
比高60m程の山にあり登山道も整備され登城しやすく、堀切、郭、土塁等が明瞭に残り小規模ながら中世の山城を堪能できる城である。主郭は祠のある郭より少し登った、大きな削平地の部分である。
登城口位置 ページ下部にマップ添付
| 所在地 |
兵豊能郡能勢町地黄 |
| 形式 |
丘城 |
| 現状 |
山林 |
| 築城年代 |
戦国期 |
| 遺構 |
郭、土塁、堀切等 |
| 主な城主 |
能勢氏 |
| 見所 |
郭 |
| おすすめ度 |
★★★ |
| 登城道整備 |
有り |
| 主郭まで |
登城口より10分 |
| 登城難易度 |
3 |
| 駐車場 |
なし |
おすすめ度は★が多いほど見ごたえがあり、最高★★★★★まで
登城難易度は数値が多いほど城へ到達する距離、
時間、困難さを示します。数値1~5
上記各種データの説明はコチラをクリック→ |